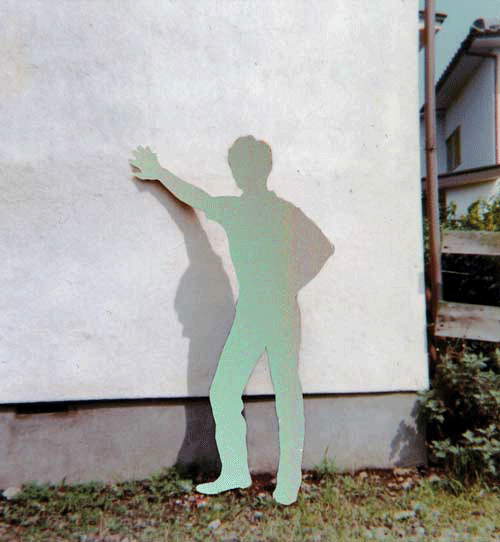
-novels space-
- 夢見妙
-
yumemimyou
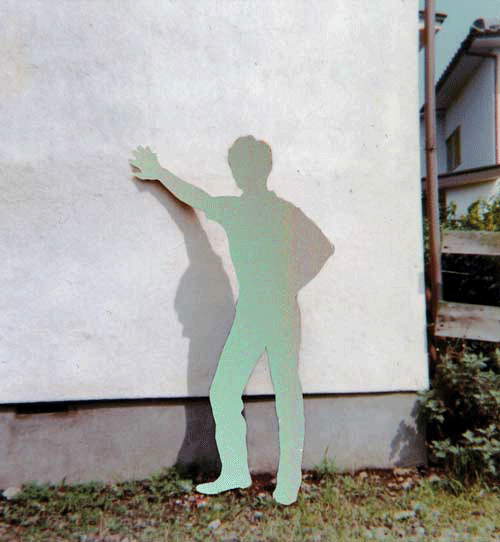
「夢、夜中にひとりで、明りも点けずに、なにやっているんだ?」ベンは龍生が、ただひたすら、なんの番組もやっていないテレビ画面に顔を寄せ、見つめている姿に不信を抱き声をかけてきた。
「砂嵐を見ているんだよ」
「砂嵐? ただ明るくザーザーしているだけじゃないか、目、悪くするぞ」
「神経を集中するといろいろな形が見えてくるんだぜ」
「何も見えないぞ、ただザーザー、うるさいだけだ、お前、大丈夫か? それって変だぞ」
「何を言うんだよ、本当に見えてくるんだよ、じっと集中して、ある形をイメージすると、その形が浮き上がってくるんだ、この砂嵐の一粒づつが僕のイメージに合わせて動き出すんだ、そして形を成す訳さ」
「そんな事出来るのか? 本当に? 信じられないな,でも、こないだの話といい、お前、ほんと,おかしいよ」
「おかしかないよ、実際、まだ単純な図形しか見る事が出来ないけど、訓練すればかなり複雑なものも見れるようになると思うよ」
「夢は、そんな事、前からやってたのか?」
「そんな事? まあいろいろと,試してはいるけど」
「ほかにどんな事をやったの?」
「そうだな、いろいろあるけれど・・・ まだ浪人をしている時に、石膏デッサンを描くための、必殺技をいろいろと編み出したよ」
「必殺技? それって、なんかヒーローものか漫画の主人公がやるやつみたいだな」
「そう、きっかけは巨人の星飛馬の大リーグボールだからね」
「エッ? なんだか急に,ばかばかしく思えてきたな」
「そんな、バカには出来ないと思うよ、実際,僕のデッサンの実力は知っているだろ? これも特訓の成果さ」ベンは首をかしげている。
「大リーグボール養成ギブスっていった感じか?」
「まあ,そんなとこかな」
「具体的には,どんな事をしたの?」
「まず、最初に考えたのが、残像を使った石膏デッサンだろ、それに、真っ暗闇の中でのデッサンに、一日中同じものをただひたすら見つめるっていうのもやったな、これをやると、そのものの存在感がいろいろと変化して見えてくるんだ。これは今でも対象物を変えて時々やるけどね、今でもやるとまた違った見え方をしたりするんで、新しい発見があるんだ、これはジャコメッティに由来するんだけれどもね」
「フーン・・・、ところで残像って、特訓しなくても見えるんじゃないのか?」
「それが、ちがうんだな、そんじょそこらの残像とはわけが違う、どう違うかってえと、さあお立会い、ご用とお急ぎでない方は、ご覧いただきたい、寄ってらっしゃい見てらっしゃい」
「おーい夢ちゃーん、どこ行っちゃうんだよー、もどって来ーい」
「冗談はさておき、さあ寄った寄った、はいはい、ここまでだよ、この線から入ってはいけないよお」この冗談わかるかな。
「まだ続いているのかよ、もういいから、話を戻してくれ、頼む、おねがいだから」
「そんなにお願いされたんじゃあ仕方がない、話してやるか」
「なんだその態度は、いやなら、もう話さなくていいよ」
「あっ、ごめん、話すから、聞いて」
「聞いてだと、聞いて下さい、お願いします。ベン乃蒸さまだろ。なんか変だな、こっちまでおかしくなるな」
「こんな人は、ほっといて」「ほっとくな」
「この残像は、ただうっすらとした影なんかじゃあないんだ、かなりリアルに映し出すんだ、例えて言えば、アニメの一コマ一コマを少しづつ、ずらして描く時に、絵の上に紙を重ねて素早くめくり、位置の確認をするのと基本的には同じ様な方法なんだけど。
僕たちの頃の美大受験の石膏デッサンの場合、木炭紙の中にほぼ実物大の石膏を描く事が基本のようになっていただろう、今の受験は違うかもしれないけどな、毎年変わるからね。そこでみんなスポークや竹串などの、はかり棒で一生懸命、位置をはかって描いていたよな、僕はそんな事はしないで、残像を使っていたのさ、石膏をじっと見つめ、網膜に焼き付けてしまうのさ、それもかなり、リアルにね、そして木炭紙を見つめればそこにはそのままの像が見える、あとは、見えている像に合わせて描いていけば大まかな全体像が描けてしまう、という事なんだけど、まあこれは、この時にしか使えないものだったけれどもね」
「べつにワシは、はかって描けばいいって感じだな、そして他のは?」
「お前さ、もうちょっと物事を建設的に考えてくれないかな」
「ワシは別に建築家じゃないから」
「そういう意味じゃなくて、それにそのワシ、ワシっていうのも以前から気になっているんだよな、まあいいや、あっ、そーだ、言い忘れてたんだけど、さっきの残像の技をやるときは、まずザンゾーケンて大きな声で叫ぶんだ」
「なんだそれ」
「たいがいヒーローもので必殺技をやるときには、その技の名を言うだろ、ちなみに、ザンゾーケンのケンは漢字で書くと拳ではなくて見なんだけどね」
「どーでもいいよ、そんな事、だいたい、それって冗談だろ」
「そう、冗談、えーと次は、暗闇でのデッサンだ」
「こら、あっさり受け流すな、ほんとに、どこまでが本当でどこまでが冗談だか、わかりゃしない」
「全部本気だよ」
「本気と本当とは違うだろ」
「どうでもいいんじゃない、そんな事、じゃ、次は」
「おい、置き去りかよ」
「あんまり気にするな、身体に悪いぞ」
「オオ、そうだなって、違うだろ、まあいいか」
「実はある時期から、物の見え方、と言うか在り方が虚無的というと、ちょっと違うか、虚構、空虚、希薄、と言うか、ようするに、なにを見ても物としての存在感が薄く感じてしまうようになってしまい、何と言ったらいいのか、実際のものを見ていると言うより映像的な質量のないものを見ていると言った感じがして、町並みを見ても人々の生活が、非現実的に見えてしまい、むなしく感じた事があるんだ。当然、絵にも反映してくる訳で、石膏デッサンを描いても、リアルに物が感じられて表現できていると思っていると、次の瞬間、空間にそのものは溶け込み消え去ってしまうといった感覚が続き、悩んでいた事があったんだ」
「それ、ちょっと精神が病んでいたんじゃないのか、今でもそうかもしれないけど」
「そうじゃないと思うよ、その当時、存在感をより強く感じようとすればするほど、希薄に感じてしまう、つまり、相対的に逆方向の力が働いてしまい結果的に思考とは反対の視覚的現象が生じてしまうのかもしれないな、それは、いわゆる精神の・・・」
「また、何だか、訳のわからない事を言い出しそうだな」ベンは思った。
「そんな時にある記事を読んだんだ、その内容はと言えば、外国の話なんだけど、ある成人女性が角膜移植か何かの、はっきりとは覚えていないんだけど、手術をしたんだ、彼女は生まれた時から失明をしていて、手術は成功し、視力も回復したのだけれど、問題が起きたんだ、目で見ただけでは、コーヒーの入ったカップでさえ、認識する事が出来なかった。手で触れて始めて、それが何なのか、どういう形をしているのかが理解できたというんだ、ちなみに手で触って始めてコーヒーと分かった時には、そのコーヒーがあまりの熱さで火傷をしてしまったとさ」
「その火傷の話ウソだろう」
「うん、ウソ」
「いい話だと思って聞いていれば、なんで変なウソを付け足すかな」
「ちょっとした病気」
「まあいいや、結構面白い話だよ、それでどうしたの?」
「彼女にとって周りの風景は平面的色彩模様でしかないのである。したがって、コーヒーカップも色の模様にしか見えず、丸い筒状の中にコーヒーが入っているという、構造的見方が出来なかったのである」
「始まっちゃったよ、夢の困った病気が」
「ここで知りえる事象は、見るという行為そのものは、それだけでは物自体の構造的部分までを認識するには、いたらず、触れたり、叩いたり、舐めたり、嗅いだり、聞いたりといった、五感のすべてを使って、認識し、多くの情報を記憶しているからこそ、理解できるのだと言う事で、裏を返せば、目で物を見ると言う行為は、あまりにも、あいまいな要素があるという事に他ならない。機能障害を起こせば違った様に見えてしまう、たとえば色盲の人のように。
しかしすべての人が、色盲であったとしたら、それは正しくなる。なぜなら大多数の意見は正しいとされるのが人間社会のルールなのであるから、良いとは思わないが。 話はそれたが、これらの事を突き詰めていくと、曖昧さと言う点では、五感すべてに言える事である」
「まだ続くのか、もういいんじゃないか、聞こえていないな」
「私はこの頃、すべての存在に対して疑問を感じ始めた。そして、この疑問の答えを導き出すために、私は、見つめる事、描く事から始めようと思った。そして最終段階は、五感を更に超えた、未知なる感覚、超感覚を身につける事であると感じていた。 私が最初に行なった事は、光のほとんど届かない真っ暗な部屋で石膏を描くと言うものであった」
「夢見の話しはよくわかった。ちょっとトイレにいってくる」
「まて、まだこれから話が始まるんだから、黙って聞け」
「エー、まだこれからかよ」
「そう、これからが面白いんだから、実験は二階の八畳の和室で行なった。襖や雨戸の隙間に黒いテープを張り、なるたけ光が入らないようにした。もちろん、作業は夜である。これなら光は入らないだろうと、明りを消して、部屋の中央に置いたラボルトの石膏像を見つめる。いくら凝視しても、ただ限りない暗闇である。目を開けても、閉じても変わらず、ただひたすら闇である。なにも見る事は出来ない。どのくらい見つめていたであろう、目も暗闇になれてきたのか、微量な光が襖に張ったテープの隙間から漏れているのが見えてくる。しかし石膏像を認識できるほどではない。像から目をそらした瞬間、薄っすらと像を認識する事が出来た。そこで私は、目をそらしては、また像の方を向き、またそらすといった行為を繰り返し行なった。ぼんやりとしたうす黒い塊が見えた。
その後、私は、そこに在るものを、目だけに頼らず、五感すべて、いや、それを超えるフィーリングで見ようと試みた。しかし、あくまでも、目を通してではあるが。
その中での、木炭によるデッサンも試みた。手元もなにも見えない状況でのことである。何がどう描けているかなど、なにも分からない手探りでの作業である。部屋の明りを点けて、どんなものが描けたか、興味津々にクロッキーブックを見る、意外とそこには、迫力のある黒い塊が描けていた。それはなにと言ってハッキリした形態はないが、なにか心に訴えてくるモノを感じる事が出来た。私は、これだと確信した。
その後、より完璧な暗闇にするために、先ほどの部屋の中央に内側を墨汁で真っ黒に塗った大きなダンボール箱を置き、その中にやはり黒く塗った石膏像を置いた。
私は深夜、部屋の明りを消し、その中に入った。ダンボール箱には扉のように、開く箇所を作り、光が漏れないように扉の縁は二重に段ボールを張り巡らした。
完全に暗闇である。目を開こうが閉じようがなにも変わらない。
実際、私は、目を開けているのか閉じているのか分からなくなっていた、妙な感覚に襲われる。自分自信の存在がどこへいったのかと不安にさえなる。
そこで私は、まず右手で自分の左手を確かめ、その後、手探りで石膏像を確かめた。
いくら見ようとしても今度は、なにも見えない。なにも見えないと言う事がどういう事なのかと言う事が感じられてくる。
いつも寝るときは目を瞑り部屋も暗くしている。それは当たり前の事である。
目を開けているにもかかわらず、ねむる時のようなのである。このままでは自分がいつ寝てしまうか分からないと心配になる。目の見えない人は常にこの状態なのかと改めて驚く。ただし、この実験では、光りを遮断した完全なる真っ暗闇の中という状況の違いはあるのかもしれない。なぜなら、人間と言うものは、いや人間に限らないのかもしれないが、特殊な状態においては、目意外の感覚で光などを感じる事も出来ると聞いたことがある。
私は、その箱の中で横たわってみた。いつしか私は・・・・・・。